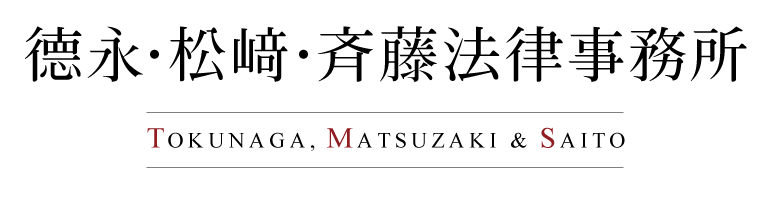監視義務に関する裁判所の視点
2025年01月16日更新
- 取締役の善管注意義務・忠実義務の一つに,自己が直接担当していない部門において違法な行為が行われないように監視する義務(監視義務)が含まれています。その監視義務に関して裁判所は,経営者の判断を尊重する一方で,厳しい視点で判断を下すこともあるようです。
- まずは,経営者の判断を尊重した判例ですが,監視義務違反を認めた高裁判決を最高裁が取り消した,というものがあります。
一つ目が,「親会社が子会社A社の発行済株式総数の67%(議決権総数の2/3超)を保有していたところ,A社の32%の株式を保有するB社から,時価評価額1万円のA社の株式を5万円で買い取った」というH22年「アパマンショップ事件」です。東京高裁は,①親会社は特別決議ができる2/3超の株式を保有しているのに,さらに32%の株式を買い取る必要性,②5万円以下の安い価格でも買い取れたはずなのに,その交渉がなされていない,として取締役の責任を認めました。しかし,最高裁は,③親会社が事業再編を進めるうえで円滑な取得が必要であったこと,④株式の評価額は一つではないこと,⑤取得に関して弁護士の意見書も徴求していることを理由に責任を認めませんでした。
二つ目が,「大学等の取引先からシステムの受注・納入・稼働確認等を担当していた営業部長Pらが4年間にわたり,取引先からの注文書,検収済証等を偽造して架空売上を計上していた」というH21年「日本システム技術事件」です。東京高裁は,①営業部がシステムの受注,納品,稼働確認をすべて取り仕切っており,上層部が簡単に架空売上を計上できる状況であったこと,②売上金の支払が2年以上も遅滞していたのに財務部が取引先に直接確認していないのは財務部としての職務として不十分であったこと,を理由として取締役の責任を認めました。しかし,最高裁は,③この会社では,営業を担当する営業部・伝票書類を確認する部署・納品したシステムの稼働を確認する部署・経理を担当する部署といった具合に職務をいくつかの部署で分掌しており,注文書,検収,売上計上の手順も定め,第三者である監査法人が定期的に取引先に残高を確認しており,通常予想される架空売上を防止できる体制が整えられていたこと,④上記架空取引の手口は,Pらが部下数名と共謀し,偽造した取引先の印鑑を用いて注文書を偽造,検収書を偽造し,監査法人からの残高確認に対しても,営業部の担当者が取引先に赴き回答書を回収したうえで虚偽の金額を記入するという,過去に同種の手口もない方法で行われていること,⑤財務部が営業部に対して,入金遅滞の理由を尋ねたところ,「取引先でシステムの稼働が遅れている,予算が獲得できなかった」という理由を挙げたが,過去に取引先との間でトラブルもなく,残高確認書も返送してきたことから,財務部も架空取引であったことには気づかなかったことを理由に責任を認めませんでした。 - この傾向の裁判例をもう少し紹介すると,R3年熊本地裁「肥後銀行事件」があります。この事件は,「業務統括部に所属していた行員Qが月100時間超の時間外労働を4か月継続し自殺したことに関して銀行が140百万円の賠償金をQの遺族に支払った。自殺3年前に監査部が業務監査部に対する監査を行い,『長時間労働がなされ,従業員の健康状態も懸念されるので,業務分担の見直しによる早急な改善が必要である』旨の報告がなされており,取締役もこの状態を把握していた」という事案です。裁判所は,取締役に監視義務違反なしと判断しましたが,その理由は,①銀行全体として,従業員が使用するパソコンは20時以降使用できない等長時間労働を抑止する方策が取られていたこと,②銀行全体として,労働時間削減の施策は実施していたこと,③Qは銀行で禁止されていたデータの持ち出しを行い,銀行の管理していないパソコンで作業をしており,直属の上司はQの長時間労働を知ってはいたが正確に把握しておらず,銀行の想定外の方法での労働であったこと,というものです。
- しかし他方で,R4年東京地裁「世紀東急工業事件」というものがあります。この事件は,「会社が同業者との間で,アスファルト材の価格を共同して引き上げるカルテルを締結し,公取委から28億円の課徴金の納付を命じられた。カルテルは,会社の事業部門に属する者が関与していた」という案件について,このカルテルに直接携わっていない社長の監視義務が問われたものです。裁判所は,社長はカルテルの存在を知っていたか,知り得たはずであるとして,社長の監視義務違反を認めましたが,その理由は,①会社の売上の多くはアスファルト材で占められており,その価格は会社の売上,利益に大きな影響を与えるはずであり,事業部門の長らは,価格を引き上げる際に,経営会議で内容を説明しているはずであること,②仮に,経営会議のメンバーがカルテルの存在を知らなかったとすると,経営会議で価格の引上げが審議された際,競争関係にある同業者があるなかで単独で値上げをすれば売上が減少するおそれがあり,その点についての議論がなされるはずである。しかし,現実には経営会議においてそのような議論がなされていない。ということは,経営会議のメンバーはカルテルの存在を認識していたと思われること,③百歩譲って経営会議のメンバーはカルテルの存在を知らなかったとしても,アスファルト材の重要性が高いことから考えて,経営会議において,事業推進本部長以外の執行役員,取締役においても,価格を引き上げる過程,内容について不合理な点がないかチェックする必要があったこと(仮に,取締役が経営会議において,値上げに至った経緯について確認しておければ,カルテルの存在が明らかとなり,その実行がなされなかった可能性が高いが,そのチェックを怠ったため,カルテルが実行されてしまったと考えられること),というものです。
この裁判例は,2・3で記載した裁判所の傾向とは打って変わって,経営者の監視義務のレベルを最高に引き上げることを求めております。特に,②の経営会議で議論がなされなかった=カルテルの存在を知っていた,③の会社にとって重要な事項を決定するのであれば,常にその決定過程に違法な点がないか確認せよ,という筋道は行き過ぎと思われます。とはいいつつ,経営を任される立場になった以上は,日頃より,アンテナを張り巡らし,「えっ?」と思う気付きのセンスを持ち,たとえ自己の担当する部署以外での出来事であっても,代表者の提案であっても,問いただす,ということは励行すべきと思われます。