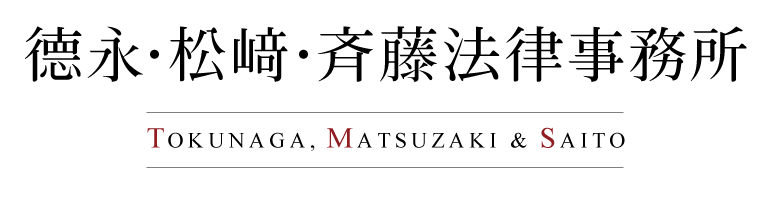株券の発行前にした株式譲渡の効力について,譲渡当事者間においては有効であると判断した裁判例~最高裁R6.4.19判決~
2025年04月25日更新
- はじめに
特に中小企業に対するM&A事案においては,法務デュー・デリジェンスの過程で,過去の「株券の交付のない株式譲渡」の事実が発覚し,果たして現在の「株主」が法的に有効な株主と言えるか(過去に株式を保有したことのある者から,将来「自身が今でも株主である」と主張されるリスクは無いか)が問題になることがよくあります。
この問題には様々な論点があるのですが,「株券発行前の株式譲渡についての当事者間での効力」について最高裁が判断を示しましたので,ご紹介させていただきます。 - 事案の概要
本判決の実際の事案は複雑ですが,判決要旨に関係する限りで簡素化すると,次のとおりです。
① A社は,株券発行会社(定款において「株券を発行する」旨の規定がある会社のこと。未だ株券を発行していなくても「株券発行会社」)。
② 被上告人Yは,A社の設立時の株主。その後,第三者Bに対して本件株式を譲渡した。その時点でA社は株券を発行しておらず,譲渡当事者間でも株券の授受は行われなかった。
③ 上告人Xは,その後,本件株式を譲り受けた者。
④ XがYに対して「Xが株主である」と主張したところ,Yは「YによるBに対する株式譲渡は,株券発行前に株券の交付なく行われたものであるから,会社法128条1項により無効であるため,Xは株主でない」と反論した。 - 問題の所在(会社法128条)
- 会社法128条は次のように規定しています。
① 1項:株券発行会社の株式の譲渡は,株券を交付しなければ,効力を生じない。
② 2項:株券の発行前にした譲渡は,株券発行会社に対し,その効力を生じない。 - 「株券発行前の株式譲渡についての当事者間での効力」については,この会社法128条の解釈をめぐって,学説・裁判例の見解が分かれている状況にありました。
【無効説】は,1項の文言どおり,譲渡人が会社から株券の発行を受けた上で,譲受人に株券を交付しなければ,譲渡人・譲受人の間においても株式譲渡の効力は生じない(2項は当然のことを確認した規定に過ぎない)という考え方です。
【有効説】は,2項が「株券発行会社に対し」と限定して規定しているとおり,当事者間では株券発行前の譲渡も有効である(1項は株券発行後の譲渡について規定したものである)という考え方です。
上記2④のYの反論は,無効説に基づき行われたものです。
- 会社法128条は次のように規定しています。
- 本判決の要旨
本判決は,以下のように述べて,【有効説】に立つことを明らかにしました。
① 株券の発行前にした譲渡について会社法128条1項が適用されると解すると,同項とは別に株券発行会社に対する関係に限って同条2項を設けた意味が失われることとなる。
また,譲渡当事者間での効力まで否定すべき合理的必要性があるということもできない。
従って,同条1項は,株券の発行後にした譲渡に適用される規定であり,株券の発行前にした譲渡は,譲渡当事者間においては株券の交付がないことをもってその効力が否定されることはないと解するのが相当である。
② 株券発行会社の株式の譲受人は,株券の交付を受けない限り,株券発行会社に対して株主としての権利を行使することができない(同条2項)から,譲渡人に対して株券の交付を請求することができると解される。
株式の譲受人は,譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することにより,株券発行会社に対し,株券の交付を直接自己に対して行うことを求めることができる。 - 検討
- 冒頭で述べたとおり,特に中小企業においては「株券発行会社」であり,株式が転々と譲渡されているにもかかわらず,「一度も株券を発行したことがない」という会社もあります。
従前は「これまで行われた株式譲渡は法的には全て無効」と評価されるリスクがあるとの前提で対応する必要がありましたが,この点について最高裁が明確に判断を示したことで,上記リスクを想定する必要がなくなり,実務的な意義は大きいと考えられます(もちろん「株券の発行前に株式が二重に譲渡されていた場合の効力」など他の論点は残っていますが,それでも論点が1つ減る意味は大きいです)。 - 本筋とは離れますが,上記3⑵で述べた無効説・有効説の争いに関して,今回敗れる形となった「無効説」は,会社法の大家である江頭憲治郎東京大学名誉教授の著書の他,立法担当者らの著書,東京地方裁判所の裁判官の著書などで支持されていた見解でした。
至極当然のことではありますが「どれだけ有力な学者・実務家が支持をしていたとしても,最高裁判所がその通りに判断するとは限らない」ということで,最高裁判例のない論点については慎重な検討が必要であるということを,改めて認識したところです。
- 冒頭で述べたとおり,特に中小企業においては「株券発行会社」であり,株式が転々と譲渡されているにもかかわらず,「一度も株券を発行したことがない」という会社もあります。