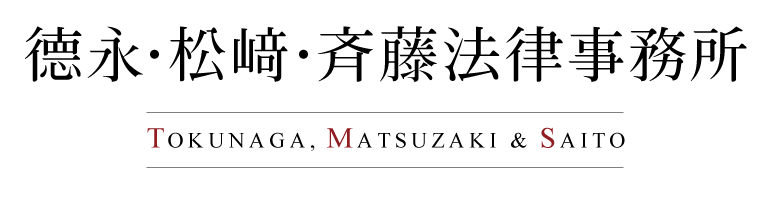法廷百景
証人尋問の心得(続)
2025年01月16日更新
- 前々回,法定百景「証人尋問の心得」で,民事訴訟における尋問と証言にあたっての留意事項の記載がありました。
会社関係の訴訟では,予期せず,証人として証言しなければならない事態になることもあり得ますので,今回は,当日の証人尋問がどのように進んでいくのか,また,そのためにどういった準備をするのか,についてイメージを持っていただこうと思います。 - 当日の証人尋問の流れ
- 裁判所への出廷
当日,裁判所に出廷したら,期日が始まる前に宣誓書に住所・氏名を記載し,押印をします。
期日が始まると,人定質問として,裁判官から住所・氏名・職業が確認されます。続いて,宣誓書をもとに宣誓します。なお,この宣誓に反して虚偽の証言をすると偽証罪として3月以上10年以下の懲役に処される可能性がありますので注意が必要です。
証人尋問は,公開の法廷で行われますので,誰でも傍聴できます。時に,裁判所見学にきた団体等がいて,傍聴人が多数になる場合もあります。 - 証人尋問
証人は,証言台に座って証言します。証言内容は録音され,記録化されますので,証言台にはマイクが置いてあります。
なお,証言台にメモ等を持っていくことはできません。記憶のみに基づいて事実を証言します。- 主尋問
まず,証人を申請した側が主尋問を行います。皆さんが証人になった場合を想定すれば,事務所の弁護士が尋問を行います。事前に証言する内容をまとめた陳述書を提出し,尋問の打合せもしますので,打合せどおりに答えていきます。 - 反対尋問
次に,相手方の代理人弁護士が反対尋問をします。反対尋問の目的は,主尋問でした証言の信用性を減殺することです。そのため,相手方は証言内容に関して不自然な点や矛盾点をつくために,速いテンポで質問を畳みかけたり,わざと証人を興奮させるような質問をしたりします。
証人としては,思い込みで回答せず,質問が聞き取れなかったり,意味が分からないときは,確認すること,また,相手方の質問に感情的に反応せず,事実を淡々と述べることが肝要です。 - 補充尋問
最後に,裁判官から補充的に質問がなされる場合があります。裁判官が特に確認したい事項について質問しますので,それにより裁判官の心証を推測できる場合があります。
- 主尋問
- 裁判所への出廷
- 証人尋問に向けた準備
証人尋問は,裁判の山場であり,判決を左右する重要な証拠調べですので,入念な準備が必要になります。事務所では,当日以外に,最低3回は尋問の打合せをしています。
まず,証人尋問の流れや留意点,証言のポイントなどを説明します。その後,主尋問で質問する事項と回答内容を打合せし,尋問の練習を行います。また,反対尋問についても,相手方からの質問を想定し,回答内容を打合せし,反対尋問の練習を行います。
最後の打合せでは,裁判所のレイアウトに似せて,証言台等を準備し,本番と同様に,尋問のシミュレーションを行います。反対尋問のシミュレーションでは,それまで主尋問の練習で(優しく)質問していた弁護士が,急に相手方代理人の立場になって,本番さながら厳しく追及するため,戸惑われる証人の方もいますが,それにより本番の方が楽に感じたという感想もいただいています。
このように,証人尋問にあたっては,念入りな準備と対策をしますので,もし証人になる場合があっても,安心して臨んでいただければと思います。